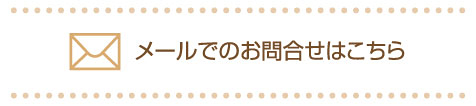■相続の流れについて学ぼう
人間はいつか死ぬもの。
その時が突然訪れることも珍しくありません。私の場合も父親が当然肺炎になり、あっと言うまに亡くなりました。
親の死によってその配偶者と子供は当然のように親の財産を相続することになります。
誰にでも訪れるであろう相続。ここでは簡単にではありますが相続の流れについて述べていこうと思います。
まずやること
おおまかな流れは以下の通りとなります。
①遺言書の確認
②相続人の確定
③遺産の調査
④相続方法の選択(3ケ月以内)
⑤遺産分割協議
⑥相続税の申告・納付(遺産が控除額以内なら不要)
⑦遺産の名義変更
①遺言書の確認
まず先に述べておくと、遺言書を残している人の割合はとても低く、1割以下と言われています。
ほとんどの家庭では遺言書を残しておらず、基本的には相続人の話し合いで相続が決まるケースが多数と言えます。
また、よく間違われるのが遺書です。遺書と遺言書は性質が大きく異なり、遺書には法的な効力は無く、遺言書には法的な効力があるということです。ですので、遺書ではなく遺言書の有無をまず確認してください。
遺言書には3つの種類があります。それぞれ法的な効力を持ちますが、自筆証明遺言書と秘密証書遺言は書き方や様式に不備があると無効になる為注意が必要です。
ではそれぞれの遺言書がどんなものか見ていきましょう!
・公正証書遺言
遺言者が公証人の前で遺言の内容を口述し、証人2人以上の立会のもと公証人がその内容を文章にまとめ、遺言者と証人が内容を確認して署名・押印することで作成される遺言書です。
公証人が書類内容を確認するので無効になる可能性がとても低い遺言書となります。
公証役場で作成します。
公証人手数料等費用がかかります。
※令和7年10月1日より公正証書遺言のデジタル化が導入され、インターネットを利用して自宅で作成可能になります。
WEBカメラ、マイクを使用しWEB上で公正証書を作成。証人も同様にリモートで参加しウェブ上で内容、意思確認され、公正証書の紙にサインは必要なく、PDF化された文書に画面を通して電子サインをすることになります。
その文書は公証役場に電子データとして保存されます。
近くに公証役場がない人、また入院中で公証役場に行くことが難しい人は是非利用しましょう。・自筆証明遺言
遺言者自身が手書きで書いた遺言書。
民法で定められた書き方や様式に沿って全文自書、日付の記載、氏名の記載、押印の要件を満たさないと無効になることがあるので注意が必要です。
2019年1月以降は、財産目録はパソコンで作成したり通帳の写しなどを使用することも認められました。
紛失はもちろん、よくテレビドラマなどである遺言書の改ざんなどのリスクがありますので、自筆証明遺言書保管制度を利用して法務局に保管するのがおすすめです。
作成には基本お金はかかりません。法務局に保管する場合は3900円の手数料がかかります。
・秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を公証人に証明してもらう遺言書です。
パソコン等を使用して作成可能で(作成した書類には記名・押印が必要)、公証人や証人を立てるのも自筆証書遺言との大きな違いでです。
自筆証明遺言と同様書き方や様式に沿わないと無効になる可能性があるので注意が必要です。
公証人費用など費用がかかりますが公正証書遺言に比べ安く収まります。
どの遺言書が良いのか?
ここではあくまでも相続の流れについて述べていますので、詳しくは専門のHPを検索して細かく内容をチェックしてください。
個人的な考えで、もし私が遺言書を作るのではあれば自筆証書遺言を作成し、専門家に書類の不備が無いかを確認し、法務局に保管してもらいます。
少し脱線しましたが、
どの遺言書にしても、発見されないと意味がありません。
遺言書については、生前にあらかじめその【有・無】と【場所】を聞いておくと楽ですが、聞いていない場合や、生前に遺言書のことを何か言っていたなぁと思いだした人で、実際の有無、場所が分からなかったどうしたらいいのか説明していきます。
公正証書遺言と秘密証書遺言は公証役場の遺言検索システムで有無を確認することができます。
ここで注意!
あくまで遺言書の有無を確認できるだけです。公正証書遺言は公証役場に原本が保管されていますが秘密証書遺言は保管されていません。
秘密証書遺言は一般的に自宅や貸金庫に保管されている可能性が高く、遺言検索システムで有りと表示された場合は頑張って探しましょう。
自筆証明遺言は秘密証書遺言と同じように自宅や貸金庫などに保管されていることが多いですが、自筆証明遺言書保管制度を利用し法務局に遺言書を保管することができます。その場合は法務局で有無を確認できます。もしこの制度を利用してない場合は家中を探しまくるか、貸金庫の存在が確認できれば貸金庫を開けるしかないと言えます。
②相続人の確定
遺言書がある場合は、遺言書に記載された人が相続人になります。(注:遺留分の請求が認められた相続人から遺留分を請求されることがあります。)
遺言書が無い場合は、亡くなった人の戸籍を調査し相続人を確定させます。
相続人になれる人、またその順位があり、前の順位の人が相続人になれば次の順位の人は相続人になりません。相続人になれる人とその順位を見ていきましょう。
| 順位 | 相続人 |
| 常に相続人 | 被相続人(亡くなった人)の配偶者 |
| 第1順位 | 被相続人(亡くなった人)の子 ※(養子も含む。子が既に死亡している場合は孫) |
| 第2順位 | 被相続人(亡くなった人)の父母(直系尊属) |
| 第3順位 | 被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹 ※(兄弟姉妹が既に死亡している場合は甥・姪) |
※代襲相続といいます。
基本的にはこれら相続人になります。
逆に被相続人と深いつながりがありもらえるだろうと思っていても相続人になれない人も見ていきます。
| 孫(代襲相続で相続人になる場合や養子縁組をしている場合は除く) |
| 内縁の妻・夫 |
| 離婚した元配偶者 |
| 義理の息子・娘(息子の妻など) |
| 再婚相手の連れ子(養子縁組している場合は除く) |
| 相続欠格・相続排除で相続できない人 |
内縁の妻・夫はもちろん、離婚した元配偶者も相続人になれませんので注意が必要ですね。
相続人になれる人、なれない人は家族間では簡単に判断できそうですが、必ず戸籍調査をする必要があります。
家族が知らない以下のような相続人がいる可能性があるからです。
| 愛人との間に生まれた子を認知していた |
| 離婚した配偶者との間に子がいた |
| 知らない人と養子縁組していた |
上記の相続人は、故人が隠していても戸籍には記録されます。逆に記録されていなければ相続人にはなりません。
また相続人が死亡している場合、代襲相続人を確定させる必要がありますので、死亡している相続人の戸籍も調査する必要があります。
遺産相続が全て終わって相続人が漏れていた場合はその相続が無効になってしまうため、必ず相続人を確定させましょう。
もし不安があるなら弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると数万円程度の報酬がかかりますが、簡単かつ正確に相続人を確定することができます。
③遺産の調査
相続人が確定したら実際の遺産を調査します。
遺産にはプラスとマイナスの遺産がありますので注意が必要です。
まずはプラスの遺産の大まかな物をご紹介いたします。
| 種類 | 具体的な内容 |
| 現金・預貯金 | 現金・普通預金・定期預金・外貨預金など |
| 不動産 | 土地・家屋・借地権・借家権など |
| 有価証券 | 株式・債権・投資信託・ゴルフ会員権など |
| 動産 | 自動車・貴金属・骨董品・美術品など |
| その他 | 知的財産権(著作権)、生命保険、退職金など |
マイナスの遺産例
| 種類 | 具体的な内容 |
| 借金・負債 | 住宅ローン・自動車ローンなど |
| 未払い金 | 未払いの税金(固定資産税・所得税など)・公共料金・クレジットカードなどの支払など |
大まかには上記のような物になります。
被相続人が生前に遺書やメモ、エンディングノートなどにまとめてくれていればその特定は簡単ですが、そのような物を残さず亡くなった場合はかなりの労力がかかるか場合もあります。
銀行の通帳や有価証券などが簡単に箪笥の中から見つかれば直接銀行や証券会社等に問合せできますが、見つからなかった場合は面倒ですがコツコツ故人の遺品の整理をし郵便物や銀行などのノベルティ(ティシュやカレンダーなど)などを元に各銀行や証券会社に問合せる必要があります。近年のペーパーレス化やネット銀行での口座開設が増え通帳が発行されてないケースもあり、発見の難易度が上がっています。その為故人のパソコンやスマートフォンのメール履歴を確認する必要もあります。
それでも見つからない場合は、片っ端から金融機関に故人の口座があるかを問い合わせするしかありません。
故人の口座を確認する方法は簡単で、
①個人の氏名、②住所、③生年月日 を伝えるだけで口座の有無を教えてもらうことができます。
不動産の場合は固定資産税の納税通知書や権利書が見つかれば簡単に特定できます。もし見つからない場合は市町村役場で取得できる名寄帳を取得すれば故人の所有する不動産を確認することができます。
生命保険も箪笥の中に証券があれば簡単に特定できますが、見つからなければこれもまた遺品や郵便物、メールなどで確認する必要があります。銀行とは違い一括にて確認できる生命保険契約照会制度がありますのでここで照会すれば簡単に見つかることもあります。
この制度には大手の保険会社のほとんどが加入してますが、加入していない保険会社もありますので必ずしも万全ではありませんので注意が必要です。
マイナス財産についてはまず間違いなく請求がくるのでそれに対応していけばよいですね。
④相続方法の選択(3ケ月以内)
遺産を調査した結果、相続方法を選択します。
・単純承認
プラスとマイナスの遺産の全てを相続する
・限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続すること。
簡単に言うと1000万円のプラスの遺産があり、3000万円のマイナスの遺産がある場合、
プラスの1000万円の遺産とマイナスの1000万円の遺産を相続するということです。
???と思うかもしれませんが、例えば手元に実家を残したい場合など固有の財産を残したい場合ですね。マイナスが多いからと言って全て相続放棄するより、残したい財産がある場合にはとっても有効ですね。
上記の例で言えば
実家が1000万円(プラスの遺産)
借金が3000万円(マイナスの遺産)
の場合でも1000万円だけ払えば実家を所有することができ、借金の2000万円は返済する必要がありません。
・相続放棄
相続を放棄し、プラスの遺産、マイナスの遺産全てを引き継がないということ。
この選択は相続を知った日から3ケ月以内に選択しなければなりませんので注意が必要です。
⑤遺産分割協議
遺産を相続することを選択した場合で、遺言書が無い場合、相続人全員でどのように遺産を分けるか協議しましょう。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員の記名・押印で遺産分割協議は完了します。
全員の同意が得られない場合は、家庭裁判所での調停や審判に委ねます。
私みたいな庶民ではそこまで問題はないですが、遺産がたくさんある、相続人同士の中が悪いなどがあると一番揉めるのがこの遺産分割協議です。必ず相続人全員の同意が必要で、誰か一人が反対すると話が進まなくなります。
また不動産が絡んでくるとまた厄介です。
よくあるケースで説明すると、
遺産内容:実家(不動産評価額5000万円)、預貯金1000万円
相続人:長男(実家に住んでいる)、次男(他県に住んでいる)
長男は被相続人が無くなった後も実家に住むことを望み実家は長男が貰う、預貯金の1000万円を次男に渡すから納得してくれという場合。
不動産評価額が5000万円、預貯金が1000万円なので遺産総額が6000万円。
相続人が二人なのでそれぞれ3000万円が法定相続分になり、1000万円の預貯金だけなら次男からしたら2000万円少なくなります。
長男が被相続人が死ぬまで世話をしたのでそれでもいいよというケースもあるでしょうし、兄弟仲が悪く遺産総額の半分をくれないと納得できないというケースもあるでしょう。
不動産を売却して遺産を折半するのが最も簡単ですが、長男の元々住んでいた実家に住み続けたいという気持ちも理解できます。
そのような場合の対処方法を含む、遺産の分割方法をこれから簡単ではありますが述べていきます。
■遺産の分割方法
・現物分割
・代償分割
・共有分割
・換価分割
の四通りがあります。
■現物分割
現物分割はその言葉の通り現物をそれぞれに分けるということ。先程のケースで言うと長男が実家、次男が預貯金1000万円といった分け方で相続ではメジャーな分け方となります。しかし先程述べたように分けられた価値が同等でない場合がほとんどで、その不公平感から相続人同士で揉めることがあります。
■代償分割
それぞれの遺産が公平になるようにお金で調整するのが代償分割です。先程のケースで言うと次男は法定相続分から2000万円不足していましたので長男がその2000万円を現金で次男に払うことで実家を相続することができるようになります。これなら公平になりますが長男が2000万円用意しないといけないので資力に余裕がないと正直難しい選択となります。
■共有分割
不動産の所有権を兄弟2人で分けるという方法です。所有権を持ちますので持ち分に応じた権利を主張できるようになります。先程のケースで均等に分けるとすると長男は1/2の所有権+500万円の預貯金、次男は1/2の所有権+500万円の預貯金となります。
でも普通に考えて後々のトラブルの臭いがプンプンする分割方法だと私は感じますね。なぜなら不動産の活用や売却には共有者全員の同意が必要になるからです。例えば10年後、次男が子供の教育費などでまとまったお金が必要なった場合でも長男の同意が無いと不動産を売ることができません。長男はその不動産に住んでいるので当然のように売るのを反対するでしょう。つまりは半分の所有権だけを持っていてもどうしようもないということになるからです。近年では持ち分だけの不動産を購入する業者もいますが足元を見られ安く買いたたかれたり、赤の他人に長男が住んでいる不動産の権利を半分売る訳ですからその後の長男に降りかかる災難も安易に予想できることでしょう。
■換価分割
不動産を売却し、そのお金を相続人で分ける方法が換価分割です。正直これが一番揉めない分割方法と言えますが、上記のケースだと長男が実家に住めなくなるのでこの方法を選べない理由となりますね。
基本的にこの4つの分割方法になります。
個人的な見解で先程のケースを考えてみると、代償分割か換価分割かなと思います。
代償分割の場合、長男に不動産、次男に1000万円の預貯金でまず分けて、差額分を長男が次男に分割して払うのが一番揉めないかなと思いますね。
換価分割を選ぶと長男は実家に住むことはできませんが、3000万円の遺産が入るので別に家を購入し生活するのもいいのではないかとも思います。
相続人同士で揉めないようによく話し合い一番最適な分割方法を選択しましょう。
まとまりそうになかったら早めに弁護士や税理士に相談すると良いでしょう。
⑤の補足:遺留分
遺産分割協議の中で遺留分を求めらるケースがあります。
大富豪の老人が死んだ後に愛人に遺産を全部相続させるという遺書が見つかり家族の間でドロドロとしたストーリーが展開されるドラマを見たことはありませんか?
じゃあこの場合愛人が遺産を全部相続できるかというとそうではありません。
法定相続人は遺書で指名されなくても最低限保証された遺産を受け取る権利を主張できます。これが遺留分です。
ここで注意が必要で、法定相続人の中でも兄弟姉妹だけは遺留分を主張する権利が無いということです。
遺留分を主張できる人は
・配偶者
・子供、孫などの直系卑属(孫の場合は代襲相続)
・親、祖父母などの直系尊属
となります。
■遺留分の割合は相続人ごとに異なります
配偶者と直系卑属は相続財産の2分の1
直系尊属は相続財産の3分の1
■遺留分の割合は総体的遺留分と個別的遺留分の2段階で算出します
総体的遺留分とは相続人全体に確保される財産のこと。
それを確定させた後、各相続人に割り当てられる財産を個別遺留分といいます。
分かり易く表にしてみます。
| 相続人 | 総体的遺留分 | 個別遺留分 | |||
| 配偶者 | 子供 | 親 | 兄弟姉妹 | ||
| 配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 | - | - | - |
| 配偶者と子ども1人 | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1 | - | - |
| 配偶者と父母(どちらか一人の場合) | 2分の1 | 3分の1 | - | 6分の1 | - |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | 2分の1 | - | - | なし |
| 子どものみ | 2分の1 | - | 2分の1 | - | - |
| 親のみ | 3分の1 | - | - | 3分の1 | - |
| 兄弟姉妹のみ | なし | - | - | - | なし |
上の表のようにまず全体の相続財産から遺留分で主張できる財産の割合(総体的遺留分)を出し、その中から各相続人に割り当てられる個別遺留分を出します。
例えば配偶者と子供1人、1000万円の遺産がある場合
遺書が無い場合、配偶者500万円、子供500万円となります。法定相続分ですね。
遺留分の場合(愛人に財産を譲る)
配偶者250万円、子供250万円となります。
後の500万円は愛人の手に渡ってしまいます。ちくしょー!
愛人の場合は極端な例かもしれませんが、子供間でも納得のいかない割合での遺産相続の場合も遺留分を主張してもいいと思います。
子供2人(長男・次男)、1000万円の遺産がある場合
遺書で長男900万円、次男100万円とされた場合、
次男は遺留分を主張すれば250万円の遺産を受け取ることができます。まぁ、兄弟間の話し合いで解決すればいいわけですが、遺産が1億円とかになってくると額が額なだけにやっぱり欲がでますよね。
遺留分は何もしなければ貰うことはできません。特別受益者(愛人)に対して【遺留分侵害額請求】を行使しないといけません。
もし納得のいかない相続になった場合は弁護士にまずは相談しましょう。
⑥相続税の申告・納付(遺産が控除額以内なら不要)
遺産分割協議が完了し実際に遺産を受けとる場合、遺産の合計額が相続税の基礎控除金額を超える場合に限り相続税の申告・納付する必要があります。
相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円X相続人の人数となり、
遺産の合計額がその金額以下であれば相続税の申告・納付の必要はありません。
相続税の納付期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ケ月以内にする必要があります。
詳しくは不動産相続税について学ぼうをご覧ください。
⑦遺産の名義変更
預貯金、不動産、株式などの相続手続きを進め、それぞれ名義変更を行います。
不動産の場合は被相続人から相続人へ不動産が移動する相続登記を行ないます。
詳しくは不動産相続税について学ぼうをご覧ください。
まとめ

ここまで簡単ではありますが相続の流れを述べてきました。
私個人の経験からは遺産分割協議で兄弟間でそんなに揉めることもないといういう印象ですが、みなさんはどう思いますか?
遺産額の大きさや兄弟間の不仲など人によって様々かもしれません。
揉めそうな場合は早めの相談が大事です。
もちろん弊社でも良いですし、お金はかかりますが弁護士や税理士に相談すると良いでしょう。